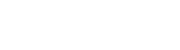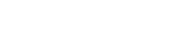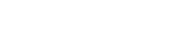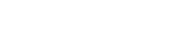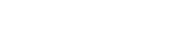通信制という選択
何かを学ぶこと、技術や学問を習得し、修めることには、本来は決まった方法はないものです。さまざまな人が、さまざまな方法でさまざまなことを学ぶのです。
そして、自分の道を見つけていきます。そのようにして、現代の学校制度が登場する以前から人は知識を深め、技術を身につけ、歴史を作り、動かしてきたのです。
基本的な学業のシステムとして、義務教育の間は朝に登校、一定数の人と同じ教室で、決められた科目教科を時間割に沿って学び、夕には家に帰るというものがありました。
学問とともに、集団生活や社会生活の基礎を作っていくことが、そこにある目的であると言えます。
ただし、そこで基礎を作ったあとの学びについては、それぞれの人が、それぞれのやり方を選べるようになっています。
なぜかと言えば、単純きわまりないことを書きますが、人はそれぞれ違うからです。
誰もが同じ人生を生きるのであれば、小学校から高校まで、そしてその先まで、同じ形の教育機関を作れば良かったでしょう。しかし、そういうわけにはいきません。
それぞれの家庭環境とか、経済状況とか、あるいは個人的な性格や才能の方向性はまったく違うのです。こういった「人の多様性」に、教育機関やその制度もまた「多様性」で応えなければならないのです。
通信制高校を選ぶ人の多くが、家庭や個人的な経済環境を理由にしていると言われています。
例えば、平日の朝から夕までは働いている人や、将来的にある特殊な分野に進もうと考えている人は、通信制、あるいは定時制という形で高校教育を受けようと考えるわけです。
何しろ、現実的な話をすれば、より良い就職先を得ようとするのであれば、高校卒業の認定が大きな助けとなるからです。それによって、その先の人生に選択肢を増やすことが出来るようになるのです。
また、通信制高校では「転入」や「編入」という入学の方法を認めています。転入とは分かりやすく言えば「転校」のこと。編入とは、別の高校を卒業せずに中退してしまった人が、入学することを言います。
さまざまな理由で、転入や編入は行われます。家庭の事情もあるでしょうし、ここでもまた個人的な事情も関わってくるでしょう。
例えば、最近では小中と同じような形の全日制のあり方に馴染めず、通信制に転入したり、いったん高校を中退して編入したりする人もいます。
いじめの問題や、精神的な負担を抱え込んでしまう人が増えている問題が、このような状況を生んでいるのです。
通信制高校は、それらの人の「受け皿」として機能します。それらの人たちに、将来の選択肢を与えるという機能を、果たすのです。